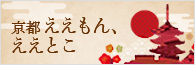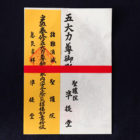江戸中期の画家・伊藤若冲の生誕から300年。京都では若冲に関する様々なイベントが開催され、記念の年を盛り上げています。ゆかりの地をめぐり、若冲の生涯に触れてみましょう。
若冲の人生は錦市場から始まった
伊藤若冲は1716年、錦市場の青物問屋「桝源」の長男として誕生。家督を弟に譲って以降は絵画三昧の生活だったというのが定説でした。しかし、近年に新資料の発見で、隠居後も錦市場の営業存続を求めて東奔西走したという、実務家の一面があったことが明らかになりました。


禅との出会い
若冲は30代の時、相国寺の大典禅師と出会います。大典禅師は彼の人柄を愛するとともに才能を見抜き、「若冲」の号を授けました。若冲は相国寺に「動植綵絵」24幅、「釈迦三尊画像」を、金閣寺に「大書院障壁画」をそれぞれ寄進。禅との出会いは若冲の人生に大きな影響を与えました。


若冲ゆかりの寺を訪ねる
若冲は、その生涯のほとんどを京都で過ごしました。妻帯せず芸事や酒も嗜まずに画業にいそしんだ若冲は、狩野派や琳派、中国絵画を研究し、独自の画風を創出。写実的、装飾的な動植物の絵画など、優れた作品を残しました。京都市内の若冲ゆかりの寺院には、彼の作品が伝わっています。



若冲が晩年を過ごした伏見
天明の大火で家を焼け出された若冲は、大阪に移り住みます。晩年は伏見に居を移し、米1斗と画1幅を交換する日々を送り、斗米翁と称しました。多くの絵を描いた傍らで、石峰寺の裏山に釈迦如来の一生を表現した五百羅漢像を作成。苔むした石仏が、今も参拝者に優しく微笑みかけています。