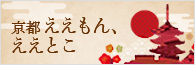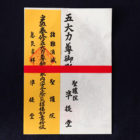応仁の乱勃発から今年(2017年)で550年。被害があまりに大きかったことから、京都では、先の戦争といえば応仁の乱を指すという俗説があるほどです。都を焼け野原にしたという戦乱の、ゆかりの地を歩いてみましょう。
応仁の乱はここから始まった
応仁の乱は、室町幕府の将軍家や管領の家督相続を巡って起こった戦乱です。畠山政長と義就の相続争いから始まった御霊神社の森での合戦が初戦となり、11年に及ぶ応仁の乱が勃発。足利義視を擁し細川勝元率いる東軍と、足利義尚を擁し山名宗全率いる西軍が激しく争い、京都の街を焼き尽くしたといわれています。

応仁の乱の戦場を訪ねる
1467年3月、年号は応仁に改まります。細川氏と山名氏がそれぞれ軍を整え、5月には両軍の陣が布かれた上京を中心に、全面的な戦闘が開始。南禅寺近辺や相国寺、船岡山などでも大規模な合戦が繰り広げられました。細川勝元と山名宗全がそれぞれ病没した後も戦乱は続きましたが、文明9年(1477)に両陣営が引き下がることで乱は終結。以後、室町幕府は衰退の途をたどります。


東陣と西陣
細川勝元は、花の御所とも呼ばれた室町第(足利将軍家の邸宅)を中心に、御構(おんかまえ)という陣地を築き、土塁や堀で周囲を防衛しました。一方、山名宗全は自身の邸宅を中心に布陣。西軍の陣地となった一帯が、西陣と呼ばれるようになりました。戦乱の爪痕は目に見える形ではあまり残っていませんが、地名や社寺の歴史からうかがい知ることができます。