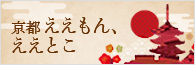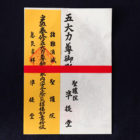秋真っ盛りの亀岡市で、紅葉狩りを楽しみませんか。創建から1300年以上と言われる鍬山神社は、口丹波指折りの紅葉名所。京都から一足のばして、山里の秋の風情を楽しみましょう。
錦秋の古社をたずねる
延喜式にその名を見ることのできる鍬山神社は、和銅2年(709)の創建と伝えられる古社。太古の亀岡盆地は、丹の湖(にのうみ)と呼ばれる赤土の泥湖だったと言われます。出雲の神々がこの地に降臨し、大巳貴神(おおなむちのかみ・大国主命)が鍬を用いて保津峡を開削。京都盆地へ水を流して肥沃な土地を造ったという伝説があり、この偉業を讃えて鍬山大明神として祀ったのが、鍬山神社の始まりとされます。


二宮の社殿が建ち並ぶ本殿
参道の橋を渡り、拝殿を過ぎると、一段高いところに本殿があり、向かって左側に鍬山宮、右側に八幡宮の二棟が並んでいます。鍬山宮のご祭神は大巳貴神、八幡宮のご祭神は誉田別尊(ほむだわけのみこと・応神天皇)。口丹波開発の神、医療の神として崇敬されるほか、縁結びや安産のご利益を求めて参拝者が訪れます。


紅葉で埋め尽くされる境内
普段は静かな神社ですが、秋には参拝客で賑わいます。彼らのお目当ては、境内を埋め尽くす、燃えるような紅葉。参道脇の深紅の紅葉も見事ですが、安産石の側にそびえる大モミジや、心字池に映り込む紅葉は必見の美しさ。京都市内の紅葉名所ほどには混雑しないので、ゆっくり鑑賞できます。フォトジェニックな秋の鍬山神社で、紅葉が織りなす綾錦の世界を満喫しましょう。