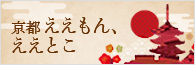その昔、京都には、美しく、高い教養を身に付けた「吉野」の名跡を受け継ぐ太夫がいました。中でも稀代の名妓と言われた、二代目吉野太夫ゆかりの寺である鷹峯の常照寺で、今年も吉野太夫の花供養が行われました。
吉野太夫が篤く信仰した常照寺
常照寺は1616年、本阿弥光悦の光悦村に、日乾上人によって開創され、さらに僧侶の学寮が開創されました。「鷹峯檀林」と称された学寮では、実に数百人もの僧侶が学んでいたそうです。また二代目吉野太夫ゆかりの寺としても知られています。太夫は26歳のとき、豪商で文化人の灰屋紹益の妻となります。しかし病気のため38歳でこの世を去り、遺言により常照寺に葬られました。境内には太夫の墓があり、今も芸事を生業とする人などが訪れています。常照寺の入口には、太夫から寄進された「吉野門」という山門を見ることができます。


吉野太夫を偲ぶ花供養
吉野太夫の花供養は、毎年4月の第二日曜に行われています。一番の見どころは現在の島原太夫による「太夫道中」。きらびやかな衣装に身を包み、高下駄を履いて源光庵から常照寺までの道を進みます。禿(かむろ)や引舟を従えて、内八文字で歩く姿は凛として美しく、当時の吉野太夫を思わせます。その後、法要や吉野太夫の墓前供養が行われ、野点席では島原太夫によるお点前が行われることも。桜に彩られた華やかで趣のある境内で、訪れた人々は太夫に思いをはせながらゆったりと過ごしていました。