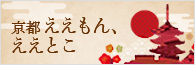織田信長公と言えば、戦国時代に天下統一の流れを作った中心的な人物の一人。そんな信長公を祀る神社が、西陣の船岡山にあります。信長公の功績を今に伝える、建勲神社の「船岡大祭」を紹介します。
織田信長公を御祭神とする建勲神社
建勲神社は明治2年(1869年)に織田信長公の天下統一の功績を称えて、明治天皇の御下命によって創建されました。「建勲」の神号を賜り、国家のために特別な功労があった人物を祀る「別格官弊社」に指定されています。明治43年には、社殿が現在の船岡山山頂へと遷移されました。
大鳥居から石段を100段ほど上った先に、拝殿や本殿があります。境内や裏手の船岡山公園からは、比叡山や如意ケ嶽(大文字山)などの山々を望むことができます。


御鎮座当初から続く船岡大祭
建勲神社では信長公が入洛した10月19日を記念して、毎年「船岡大祭」が開催されています。午前11時になると宮司によるお祓いがあり、まず本殿で神事が執り行われます。その後、拝殿で、信長公ゆかりの仕舞『敦盛』や『小鍛冶』などが奉納されるのです。『敦盛』は信長公が特に好み、桶狭間の戦いの前夜にも舞ったのだとか。境内には、敦盛の一節が記された石碑を見ることができます。「人間五十年……」と力強い台詞で始まった仕舞は、訪れた人々を魅了していました。




多彩な演目の奉納も見逃せない
仕舞に加え、今年は舞楽『右方 抜頭』や『東日本・熊本大震災の鎮魂と復興の祈りの奉納舞』、修心流居合術兵法が奉納されました。しなやかで美しい舞や迫力ある居合術など、一つ一つの演目にならではの魅力が。また建勲神社では数年に一度、火縄銃三弾打奉納が行われます。今年は行われませんでしたが、来年以降は大迫力の奉納を見ることができるかもしれません。訪れた人々は信長公に思いを馳せながら、充実した秋のひとときを過ごしていました。