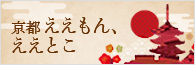「ほうこくさん」の愛称で親しまれる豊国神社は、天下統一を果たした戦国大名・豊臣秀吉を祀る神社です。神社やその近隣には、今でも豊臣秀吉ゆかりの遺構が残っています。毎年、新暦の豊臣秀吉の命日に行われる例祭を紹介します。
豊臣秀吉が御祭神の豊国神社
豊臣秀吉は死後、遺命によって東山阿弥陀ヶ峰の山頂に埋葬されました。その山腹に建てられた廟所が、豊国神社の始まりといわれています。
廟所は朝廷より「豊国乃大明神」の神号を賜り、遷座式で「豊国神社」と命名されました。しかし大坂夏の陣で豊臣家が滅亡すると、徳川家によって神号は剥奪され、社領は幕府に没収されてしまいます。社殿は残されたものの、時の流れとともにそのまま朽ち果ててしまいました。現在は、明治時代に天皇の命によって再興された当時の社殿を見ることができます。



優美や神楽舞が見物の「例祭」
川端通から正面通を東へ進むと、豊国神社の大きな鳥居が見えてきます。豊臣秀吉の新暦の命日にあたる9月18日に行われる例祭は、豊国神社が再興された1880年から続く伝統的な行事。午前11時から神事が行われ、続いて巫女による神楽舞が奉納されます。太鼓や笙の音に合わせ、榊を手にした巫女がゆっくりと舞い始めると、美しくしなやかな舞で訪れた人々を魅了していました。
また例祭の翌日には、献茶会が行われます。薮内流家元により、薄茶と濃茶が秀吉と正室の北政所を祀る貞照神社に奉納されるのです。




8のつく日の「おもしろ市」
また豊国神社では、8のつく日に境内で「おもしろ市」が開催されています。日にちによって内容が異なり、8日は古布や骨董の市、18日はフリーマーケット、28日には手作り市が行われています。
例祭が行われた日は、フリーマーケットが開かれていました。服やアクセサリー、雑貨やおもちゃなど様々な商品が並び、どれもお買い得価格で思わぬ掘り出し物に出会えそうな予感。例祭に合わせて「特別御朱印」が授与されていたこともあり、たくさんの人が市を訪れ、買い物を楽しんでいました。