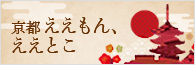烏丸鞍馬口から、東へ住宅街を進んだところにある御霊神社。上御霊神社とも呼ばれ、毎年5月には洛中で最も古いとされる祭の「御霊祭」が行われます。
応仁の乱が勃発した御霊神社
御霊神社は794年の平安京遷都の際に、崇道天皇を祀ったことに始まります。その後、非業で亡くなった高貴な方々の神霊が合祀され、現在は八柱の神霊が祭神になっています。かつて疫病や天変地異が起こると、怨霊の仕業と考えられていました。863年には御霊を鎮めるための御霊会が催され、これが御霊祭の起源と言われています。
また、応仁の乱が勃発した地でもあります。1467年に家督を争っていた室町幕府菅領の畠山政長と畠山義就との戦いが御霊の森で起こり、応仁の乱へと発展。戦いは各地に広がり、10年以上続きました。


千年以上続く「御霊祭」
毎年5月に行われている「御霊祭」は、千年以上続く歴史ある祭。5月1日の神幸祭に始まり、17日の宵宮、18日の還幸祭と続きます。
宵宮では屋台がずらりと並び、祭ならではの華やかな雰囲気に。御霊太鼓の演奏も行われ、地元の人らでにぎわいます。祭の期間中、拝殿には神輿が置かれています。小山郷・今出川口・末廣の三基の神輿は、還幸祭で御霊太鼓、剣鉾、早乙女、稚児、若武者、牛車、獅子舞と共に氏子町を巡幸します。




氏子町を行くにぎやかな行列
御霊祭で最も盛り上がりを見せるのが、18日の還幸祭。午前11時半から、まず「渡御の儀」が執り行われます。そして午後1時頃になると、いよいよ行列が出発します。行列は神社を出て出町桝形商店街のアーケードを通り、京都御苑内へ。その後も氏子町を練り歩き、再び神社に戻るのは、夕暮れが迫る頃になります。
巡幸が始まると、威勢の良い掛け声と、シャンシャンと鳴鐶(なりかん)の音が氏子町に響き渡りました。出町桝形商店街のアーケードの通り抜けや神輿の差し上げなど、様々な見どころも。今年も多くの人が沿道に集まり、行列を見守っていました。