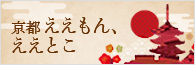京都最古の神社で世界遺産にも登録されている上賀茂神社(賀茂別雷神社)は、厄除けや方除けなどの神として広く信仰されてきました。豊かな自然に囲まれた広大な境内では、例年3月下旬から4月中旬にかけて、様々な桜が見頃を迎えます。境内に咲き誇る、由緒ある桜を紹介します。
参道脇に咲く、「斎王桜」と「御所桜」
一の鳥居から一直線にのびる参道の脇には、二種類の桜の古木があります。
一の鳥居側(南側)にあるのは、樹齢150年以上とも言われる、紅枝垂れ桜の「斎王桜」です。斎王とは、かつて宮中から神さまにお仕えするために遣わされた未婚の皇女のこと。上賀茂神社には、平安時代から鎌倉時代にかけて遣われされていました。見頃を迎えた斎王桜は、枝いっぱいに鮮やかな紅色の桜を咲かせます。
二の鳥居側(北側)にあるのは、早咲きの「御所桜」。孝明天皇が京都御所より御下賜された枝垂れ桜です。大きく広げた枝に可憐な淡いピンク色の花を咲かせます。


伝統行事「賀茂競馬」の馬場沿いの桜
上賀茂神社では、毎年5月5日に「賀茂競馬(かもくらべうま)」が行われます。1073年に堀河天皇が宮中武徳殿で行われていた競馬会式を上賀茂神社に移したことに始まり、二頭の馬が馬場を駆け抜け、速さを競うものです。
馬場の西側には、桜の木が並んでいます。一の鳥居近くには「馬出しの桜」。その名のとおり、賀茂競馬のスタート地点の辺りに植えられています。
さらに二の鳥居方向へ進むと、「鞭打ちの桜」と呼ばれる桜があります。こちらは乗尻(騎士)が鞭を打つタイミングの目安となっている桜です。


趣のある二つの枝垂れ桜
参道を進み二の鳥居前へ行くと、紅枝垂れ桜の「風流桜」があります。5月に行われる葵祭では、この風流桜を目印に風流傘と花傘が並べられます。
境内へ進むと細殿(拝殿)の左奥に、「みあれ桜」と呼ばれる、ひときわ目を引く華やかな桜があります。葵祭に先立って行われる神迎えの神事「御阿礼(みあれ)」の際に、この桜の下を神幸するのです。
二の鳥居から細殿や立砂(御祭神・賀茂別雷神が降臨した、上賀茂神社の裏手にある「神山」を象ったとされているもの)とともに眺めるみあれ桜は、格別な趣があります。
上賀茂神社を訪れ、由緒ある桜をゆっくりと楽しんでみませんか?